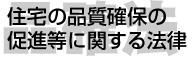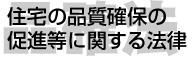|
|
 |

|
 |
 |
「住宅品質確保促進法」とは何ですか? |
 |
 |
平成12年4月1日から施行された新しい法律です。(1)施行日以降に売買・請負契約された、すべての新築住宅の基本構造部分などについては、10年間瑕疵担保責任をもつこと(2)住宅の性能を表示するための制度ができること(3)建設性能評価書の交付された住宅の紛争処理のための制度ができることなどを柱にした法律です。 |
|
 |
 |
この法律で使われる、「住宅」などの言葉の定義を教えてください。 |
 |
 |
住宅:人の居住の用に供する家屋または家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)
新築住宅:新たに建設された住宅で、まだ、人の住居の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)一戸建て住宅・低層共同住宅・マンションなどの共同住宅などの、すべてが対象になると考えればよいでしょう。店舗付き住宅などは、その住宅部分が対象になります。
建築工事が完了した日とは、工事のすべての過程(施工者による検査を含む)を終了して、注文者・買主への引渡を残すのみという段階を言います。 |
|
 |
 |
ところで、なぜ、住宅の性能を表示するのですか? |
 |
 |
住宅生産者は、自社の商品や仕様をお客様に説明するとき、様々でばらばらな方法で行ってきました。当然のことながら、自社の強みを強調できるような部分へ説明が集中するのはやむを得ないことです。しかし、お客様の立場からすると、本当に自分が希望する住宅になっているのか、間違いのない選択をしたのだろうか、ということが、ともすれば分からないことになります。そこで、国土交通省では、住宅の性能を表示するのであれば、こんな項目について、こんな方法で行えばよいのではないかと新しい制度を作ったわけです。この制度は、あくまで任意です。お客様と、住宅生産者がよく話し合って採用を決めることになります。 |
|
 |
 |
性能を表示するための基準などはどうなりますか? |
 |
 |
国土交通大臣が、建築審議会に諮って、「日本住宅性能表示基準(住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準)」を制定しました。さらに、表示のための評価方法や検査方法として「評価方法基準」が定められています。
「日本住宅性能表示基準」については、戸建住宅、共同住宅(住戸部分及び住棟部分)ごとに定めています。また、「評価方法基準」は、工法によって内容を区分して定められている場合もあります。 |
|
 |
 |
評価方法基準とは、具体的にはどんな手続きになるのですか? |
 |
 |
この制度に基づいて、これから建設する住宅の性能表示をしようとするときは、まず、設計段階で、事前自己評価をした上で、設計図書など申請書類を、「指定住宅性能評価機関」に持ち込み、評価してもらいます。このとき、機関から交付されるのがマーク付きの「設計住宅性能評価書」です。又、この機関が工事中(完成時を含む)に原則4回の検査をした上で交付されるのがマーク付きの「建設住宅性能評価書」です。
なお、これらの「評価書」を契約書に添付した場合等は、評価書にかかれた性能のある住宅を建設することを契約したものと見なされます。ただし、契約書の上で、項目を排除することはできます。 |
|
 |
 |
「性能表示項目」とはどんなものでしょうか? |
 |
 |
「日本住宅性能表示基準」というものが、平成12年7月19日、告示されました。戸建住宅については、8つの必須項目と1つの選択項目の合計9つの表示項目があります。それは、
- 構造の安定に関すること 地震や風などの力が加わったときの建物全体の強さ。
- 火災時の安全に関すること 火災が発生した場合の避難のしやすさや建物の燃えにくさ。
- 劣化の軽減に関すること 建物の劣化(木材の腐食、鉄のさびなど)を防止、軽減するための対策。
- 維持管理への配慮に関すること 給配水管とガス管の日常における維持管理(点検、清掃、修繕)のしやすさ。
- 温熱環境に関すること 暖冷房時の省エネルギーの程度。
- 空気環境に関すること 内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさや換気の方法。
- 光・視環境に関すること 開口部の面積の大きさや位置。
- 高齢者等への配慮に関すること 加齢等に伴う身体機能が低下したときの移動のしやすさや介助のしやすさ。
以上は必須項目。
- 音環境に関すること 居室の外壁開口部に使用されるサッシの遮音性能。
この項目は選択項目 |
|
 |
 |
性能表示項目は、どんな考え方から選ばれていますか? |
 |
 |
次の様な考え方です。
- 評価のための技術が確立されていて、広く利用できるもの。
- 設計段階で評価が可能なもの。
- 外観からでは容易に判断しにくい項目を優先すること。
- お客様が容易に変更できる設備機器などは原則として対象としない。
- 客観的な評価の難しい項目は対象としない。
などとなっています。日本では、いろいろな工法の住宅が建設されていますが、ここでは、できる限り幅広い範囲の住宅が対象にできる項目としています。 |
|
 |
 |
どのような評価の表示方法をするのですか? |
 |
 |
次の3つの方法があります。
- 仕様によって、設定した「等級」を表示するもの。
- 仕様や図面の「数値」を表示するもの。
- 図面の「措置・対策」を表示するもの。
表示項目ごとに、どの方法によるかがが決められています。また、等級は、別に定める「評価方法基準」に従って評価されます。 |
|
 |
 |
「等級」とは何ですか? |
 |
 |
その住宅の仕様等が、「性能評価基準」に照らし合わせてどれだけの性能を持っているかを表したものです。等級1は、一般的に「建築基準法」で定めのある場合は、その基準に適合している状態をいいます。このレベルでも、決して悪いわけではありません。
例えば、「構造の安定に関すること」でいうと、耐震等級では、3、2、1と3つの等級があり、3が最も高く1が最も低いことになります。さらに、等級2は、等級1の1.25倍、等級3は1.5倍の性能(「構造の安定」でいえば強度)があるとされるものです。 |
|
 |
 |
「数値、措置・対策」の表示とは何ですか? |
 |
 |
性能の高さを、数値で比較して等級を決めにくい場合、事実の数値とか措置・対策の方法を、そのまま表すことです。例えば、「基礎・地盤に関する情報」の表示がそれにあたります。ここでは、その建築敷地の許容支持力の数値やその数値を得るために行った地盤調査方法、又、基礎の構造や形式を、そのまま、記入することになっています。 |
|
 |
 |
「品確法」について全体的に、話しておきたいことはどんなことですか? |
 |
 |
新しい制度ですから、理解不足や誤解が生じないように、個々の項目の説明をする前に、つぎのことは、よく理解しておく必要があります。これらのことは、国土交通省が今後まとめる予定の解説書でも記述される予定になっています。
- 表示項目の多くは、等級や数値で表現されていますが、すべてに最高ランクを要求することは合理的とはいえません。自らのライフスタイル、工事費、地域の気候・風土、デザインや使い勝手など、性能表示項目以外のことも考えて、もっとも適した性能の組み合わせで考えるべきです。たとえば、閑静な住宅地に建てる住宅に、遮音性の非常に高いサッシを設置したりするのも、特別の場合を除いて必要のないことが多いでしょう。
- 表示項目のなかには、一方を良くすると別の項目の性能が下がるなど、反対の結果になるものがあります。たとえば、採光の条件を良くするために、窓を大きくすると、音環境や省エネルギー性は悪くなります。ひとり一人が、自分の考えをしっかりもって、性能を選ぶことが大切です。
- 表示される等級や数値は、設計段階で予測できる範囲内のものとされています。しかし、住宅の性能は、様々な要因によってばらつきを生じさせることがあります。同一の設計図書に基づいて建てられた住宅であっても、どのような性能が達成されるかを正確に予測することは、最新の科学をもってしても難しいものです。そのため、ここで決められた、いくつかの性能については設計段階での予測精度に乏しいものもあります。その上での評価ですから、個人個人の実感とは異なる結果になる可能性があります。
- 住宅の性能は、地域の気候など環境の条件ばかりでなく、住まい方や維持管理の仕方の違いによって大きく影響を受けるものです。それぞれの項目では、通常予測される条件が想定されています。その想定が異なった場合、結果が違ってくることもあります。
- 住宅の性能は、特に地震や火災などの災害がなくても、時間とともに、いわゆる「経年変化」をします。この変化が進む早さや程度を正確に予測することは、現在の科学水準では難しいと云われています。そのため、評価された性能項目の多くは、評価を行った時点(完成段階)のもので、経年変化については配慮されていません。
- 住宅性能の評価には、コストと期間がかかります。機関の評価料金だけでなく、住宅性能評価を申請するための図書の作成にも、通常の図面以外の費用や時間がかかります。これらの費用は、結局お客様に負担していただくことになるでしょう。
これらのことは、住宅生産者としては、なかなか言いづらいところですが、国土交通省などの解説書がまとめられると思いますので、うまく活用して、お客様に正しく認識していただきましょう。 |
|
 |
 |
住宅性能表示制度のメリットはどんなことでしょうか? |
 |
 |
次のようなメリットを上げることができます。
- 住宅の性能を設計・施工段階で、第三者がチェックするので安心。
- 契約段階で、どのような性能のある住宅になるか明確になり、しかも、その性能を持った住宅の引渡が約束されます。
- 万一、トラブルが発生しても迅速に解決を図る裁判外紛争処理を利用できます。
- 新築時の性能が分かりますから、将来、中古住宅として売買するときときもスムーズ。
|
|

|
|