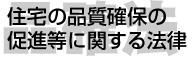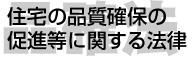|
|
| 1.構造の安定に関すること |
 |
 |
 |
 |
「構造の安定に関すること」には、どんな項目がありますか? |
 |
 |
以下のような。4つの項目で、4つの等級、1つの数値と1つの措置・対策の6つの表示があります。
- 地震に対する構造の安定 ア、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)イ、耐震等級(構造躯体の損傷防止)
- 風に対する構造の安定 耐風等級(構造躯体の倒壊防止および損傷防止)
- 積雪に対する構造の安定 耐積雪等級(構造躯体の倒壊防止および損傷防止)
- 基礎・地盤に関する情報 ア、地盤又は杭の許容支持力およびその設定方法 イ、基礎の構造方法および型式等
| |
 |
 |
「倒壊等」と「損傷」はどう違うのですか? |
 |
 |
「倒壊等」とは、構造躯体が倒壊、崩壊するなど人命がそこなわれるような壊れ方をいいます。又、「損傷」とは、構造躯体に、大規模な工事を伴う修復が必要となる著しい被害をいいます。当然、構造上の強度に影響のない、軽微なひび割れの発生などは、ここに含まれません。
なお、地震に対する構造の安定では、「倒壊等」と「損傷」は、別々に2つの項目になっていますが、風や積雪に関しては、合わせて1つの項目になっています。これは、風や積雪の場合、2つの目標を1つの方法で同時に評価することが多いためです。 | |
 |
 |
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)について説明してください。 |
 |
 |
等級の水準は次の通りです。
| 等級1 |
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度。 |
| 等級2 |
同上の1.25倍の地震力に対して倒壊しない程度。 |
| 等級3 |
同上の1.5倍の地震力に対して倒壊しない程度。 | | |
 |
 |
数百年に一度程度発生する地震力とはどのくらいの大きさですか? |
 |
 |
地域によって異なるので、一概にはいえませんが、東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度6強から7程度(地表の加速度で400cm/s2程度)に相当するといわれています。 これは、関東大震災における震源地に近い小田原で観測された地震に相当します。 その1.25倍とか1.5倍というのは、震度階では、震度7以上がありませんので、すべて震度7ということになりますが、地表の加速度で示せば、1.25倍は500cm/s2、1.5倍は600cm/s2程度です。阪神・淡路大震災では、ところによって、これらを越える地表の加速度があったともいわれています。
ちなみに、重力加速度1G=980cm/s2(gal)です。 | |
 |
 |
耐震等級(構造躯対の損傷防止)について説明してください。 |
 |
 |
等級の水準は次の通りです。
| 等級1 |
稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度。 |
| 等級2 |
同上の1.25倍の地震力に対して損傷しない程度。 |
| 等級3 |
同上の1.5倍の地震力に対して損傷しない程度。 | | |
 |
 |
数十年に一度程度発生する地震力とはどのくらいの大きさですか? |
 |
 |
地域によって異なるので、一概にはいえませんが、東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度5強程度(地表の加速度で100cm/s2程度)に相当するといわれています。その1.25倍、1.5倍というのは、 震度階では、どちらも震度5強ということになりますが、地表の加速度で示せば、1.25倍は125cm/s2、1.5倍は150cm/s2程度です。 | |
 |
 |
震度階というのをもう少し詳しく説明してください。 |
 |
 |
気象庁が発表している震度階級関連解説表の一部を抜粋しますと次のようになります。
●震度階級:5弱
人間:多くの人が、身の安全を図ろうとする。一部の人は、行動に支障を感じる。
屋内の状況:つり下げ物は激しく揺れ、棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。座りの悪い置物の多くが倒れ、家具が移動することがある。
屋外の状況:窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱が揺れるのが分かる。補強されていないブロック塀が崩れることがある。道路に被害が生じることがある。
木造住宅:耐震性の低い住宅では、壁や柱が破損するものがある。
●震度階級:5強
人間:非常な恐怖を感じる。多くの人が、行動に支障を感じる。
屋内の状況:棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる。テレビが台から落ちることがある。タンスなど重い家具が倒れることがある。変形によりドアが開かなくなることがある。一部の戸が外れる。
屋外の状況:補強されていないブロック塀の多くが崩れる。据え付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。多くの墓石が倒れる。自動車の運転が困難となり、停止する車が多い。
木造住宅:耐震性の低い住宅では壁や柱がかなり破損したり、傾くものがある。
●震度階級:6弱
人間:立っていることが困難になる。
屋内の状況:固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。開かなくなるドアが多い。
屋外の状況:かなりの建物で壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。
木造住宅:耐震性の低い住宅では倒壊するものがある。耐震性の高い住宅でも、壁や柱が破損するものがある。
●震度階級:6強
人間:立っていることができず、はわないと動くことができない。
屋内の状況:固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒する。戸が外れて飛ぶことがある。
屋外の状況:多くの建物で壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。
木造住宅:耐震性の低い住宅では倒壊するものが多い。耐震性の高い住宅でも、壁や柱がかなり破損するものがある。
●震度階級:7
人間:揺れにほんろうされ、自分の意志で行動できない。
屋内の状況:ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。
屋外の状況:ほとんどの建物で壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されているブロック塀も破損するものがある。
木造住宅:耐震性の高い住宅でも、傾いたり、大きく破損するものがある。 | |
 |
 |
耐風等級(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止)について、説明してください。 |
 |
 |
等級の水準は次の通りです。
| 等級1 |
極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)に対して倒壊、崩壊せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)に対して損傷しない程度。 |
| 等級2 |
同上の1.2倍の風の力で、倒壊又は損傷しない程度。 | | |
 |
 |
500年に一度発生する風とは具体的にどの程度の風ですか? |
 |
 |
建物の高さや形状、地域によって異なるために一概にはいえませんが、例えば、東京郊外の住宅地を想定した場合、高さ10mの位置で平均風速が約35m/s、最大瞬間風速が約50m/sの風に相当するといわれています。これは、伊勢湾台風時における名古屋気象台で記録された暴風に相当します。 | |
 |
 |
50年に一度発生する風とは具体的にどの程度の風ですか? |
 |
 |
例えば、東京郊外の住宅地を想定した場合、高さ10mの位置で平均風速30m/s、最大瞬間風速45m/sの風に相当するといわれています。 | |
 |
 |
台風の強さを教えてください。 |
 |
 |
気象庁では、台風のおおよその勢力を示す目安として、台風の「大きさ」と「強さ」を、それぞれ5段階で表現します。
そのうち、「強さ」については、次の通りです。
「弱い」:風速17〜25m/s
「なみの強さ」:風速25〜33m/s
「強い」:風速33〜44m/s
「非常に強い」:風速44〜54m/s
「猛烈な」:風速54m/s以上 | |
 |
 |
耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止)について、説明してください。 |
 |
 |
等級の水準は次の通りです。
| 等級1 |
極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法第86条に定めるものの1.4倍)に対して倒壊、崩壊等せず、建築基準法に定める稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条で定めるもの)に対して損傷しない程度。 |
| 等級2 |
同上の1.2倍の積雪による力で、倒壊または損傷しない程度。 | なお、この等級については、多雪地区内でのみ記入し、該当しない場合は、「該当地区以外」というところにチェックをすることになっています。 | |
 |
 |
積雪による力とは、簡単に言うとどんなことですか? |
 |
 |
積雪によって生じる重さのことと考えれば良いでしょう。ところで、雪の重さは、雪の種類によって大きく異なります。たとえば、新雪ではおよそ50〜150kg/m3と言われており、小しまり雪では、およぞ150〜250kg/m3、しまり雪でおよそ250〜500kg/m3、ざらめ雪ではおよそ300〜500kg/m3と言われています。 | |
 |
 |
500年に一度発生する積雪とは具体的にどの程度の雪ですか? |
 |
 |
同じ頻度で発生する雪の力による絶対的な力は、地域によって異なるために一概にはいえませんが、例えば、新潟市を想定した場合、約1.4mの積雪深に相当するといわれています。 | |
 |
 |
50年に一度発生する積雪とは具体的にどの程度の雪ですか? |
 |
 |
例えば、新潟市を想定した場合、約1.0mの積雪深に相当するといわれています。 | |
 |
 |
地盤又は杭の許容支持力等およびその設定方式について説明してください。 |
 |
 |
この項目では、等級による表示ではなく、その住宅敷地の許容支持力等の数値と、その数値を導き出した、調査方法を記入することになっています。
○許容支持力等 地盤:○○(kN/m2)、杭:△△(kN/本)
○設定方法 地盤調査方法等[ ] | |
 |
 |
許容支持力とは何ですか? |
 |
 |
ここで云う許容支持力とは、長期許容支持力を指し、ふつう、「地耐力」と呼んでいるものです。これまでは、5トンとか3トンというようにいわれていましたが、国際(SI)単位を取り入れたことにより、ニュートン(N)となりました。例えば、m2当たり30キロニュートン(30kN)は、これまでいわれていた3トンとほぼ読み替えられます。
通常、木造2階建て住宅の場合、30キロニュートンあれば、特別の地盤補強をしないことが多いといわれています。都市基盤整備公団では、平成12年4月以降に販売する宅地では、すべて30キロニュートン以上とするようになっています。
1N(ニュートン)とは、重量1kgの物体に1m/s2の加速度を生じさせる力です。つまり、1N=1kg・m/s2です。 | |
 |
 |
設定方法とはなにですか? |
 |
 |
先の許容支持力(地耐力)などを、どんな方法で調査し、定めたのかということを記載します。表示される内容は、敷地により様々ですが、調査方法(地盤の測定、過去の測定データの検討、周辺状況の調査、敷地の履歴調査、敷地の造成方法の確認など)、測定を行った方法(スウェーデン・サウンディング法、標準貫入試験など)が表示されることになります。また、地盤改良を行ったり、行われている場合には、改良後の地盤の測定方法が示されます。
住宅を建築する場合、その敷地の地盤に応じた基礎の設計・施工をしなければいけないと考えられますので、これらの事項は、お客様にとっても、生産者にとっても、大切な部分です。必ず、何らかの方法で、地盤を確認した上で、設計・施工にかかるべきでしょう。なお、周辺の住宅の基礎や地盤の状況が明らかになっている場合では、高度な地盤調査ではなく、簡単な調査でも信頼のおける情報が得られる場合もあるものと考えます。 | |
 |
 |
基礎の構造方法および形式等について説明してください。 |
 |
 |
この項目でも、等級による表示ではなく、その住宅の基礎そのものについて記入するようになっています。
■直接基礎 ○○造△△基礎
■杭基礎 杭種[ ]、杭径○○cm、杭長○○m | |
 |
 |
基礎の種類にはどんなものがありますか? |
 |
 |
ふつう住宅の場合、鉄筋(あるいは無筋)コンクリート布基礎が用いられます。そのほか、ベタ基礎や杭基礎など、その基盤と建物にもっとも適切なものが選ばれることになります。この項目では、それをそのまま記入することになります。 | |  |
 |

|
|