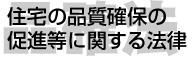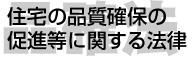|
|
| 8.音環境に関すること |
 |
 |
 |
 |
音環境に関することについて説明してください。 |
 |
 |
住宅の音については、いろいろな音の遮断性能が考えられますが、現段階での科学的な知見では、設計段階で正確に予測することは、困難であるといわれています。そこで、戸建住宅については、外壁開口部の透過損失等級だけが項目として選ばれており、しかも、この項目は「選択項目」で、必ずしも記入しなくて良いことになっています。
また、共同住宅でも選択項目ではありますが、重量床衝撃音遮断対策等級・相当スラブ厚等級・軽量床衝撃音遮断対策等級・床仕上げ等級・透過損失等級(界壁)などの等級項目があります。 | |
 |
 |
「透過損失等級(外壁開口部)」について説明してください。 |
 |
 |
居室の外壁の開口部に関する空気伝搬音の遮断の程度によって、次のような等級になっています。
| 等級3 |
特に優れた空気伝搬音の遮断性能を確保する程度(JISRm(1/3)-25等級相当以上) |
| 等級2 |
優れた空気伝搬音の遮断性能を確保する程度(JISRm(1/3)-20等級相当以上) |
| 等級1 |
その他 | | |
 |
 |
JISの等級について説明してください。 |
 |
 |
JISの等級は、実験室でのサッシによる空気伝搬音の遮断の程度の測定値をもとに判定されるものです。JISRm(1/3)-25等級程度のサッシとは、例えば100〜2500ヘルツの周波数における平均値として25dB程度の低減が測定されるサッシを指します。
JISRm(1/3)-20等級、JISRm(1/3)-25等級はともに、いわゆる「防音サッシ」といわれるものです。 | |
 |
 |
遮音性の高いサッシの取扱についての留意点は何ですか? |
 |
 |
「防音サッシ」は、通常のサッシに比較すると相当の防音効果のあるものです。そのため、外部からの騒音の進入があまりない閑静な住宅地などでは、ここまでのサッシを使用することは、一般的に少ないといえます。また、このような場合にサッシの性能のみを向上させると、逆に、ふつうでは気にならなかった室内のいろいろな音が、かえって気になってしまうという問題も指摘されていますし、「防音サッシ」は、一般的にふつうのサッシよりも重いために、よく説明しておかないと後で問題になることもあります。必要性について、お客様と十分に検討した上で、採用することが大切です。 | |
 |
 |

|
|