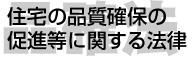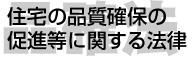|
|
| 3.劣化の低減に関すること |
 |
 |
 |
 |
劣化の軽減に関することについて説明してください。 |
 |
 |
住宅に使われている材料は、時間の経過によって、劣化します。この項目では、その劣化を軽減するための対策が、その住宅の構造躯体に対してどれだけ講じられているかを「劣化対策等級」として表します。 | |
 |
 |
「劣化対策等級」について説明してください。 |
 |
 |
構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸ばすための対策の程度を表します。土台・軸組・床組における防腐・防錆などの材料ごとの措置や、床下防湿、小屋裏換気などへの対策を評価します。
| 等級3 |
通常想定される自然条件および維持管理の条件の下で3世代(概ね75〜90年)までの期間を伸ばすのに必要な対策が講じられている。 |
| 等級2 |
同じ条件の下で2世代(概ね50〜60年)までの期間を伸ばすのに必要な対策が講じられている。 |
| 等級1 |
建築基準法に定める対策が講じられている。 | | |
 |
 |
「構造躯体等に使用する材料」とは何を指しますか? |
 |
 |
木材、鋼材、鉄筋コンクリートなどを指します。 | |
 |
 |
「大規模な改修工事」とは、どんなイメージですか? |
 |
 |
劣化した柱・梁・壁などの全面改修といった工事を想定しています。 | |
 |
 |
「通常予想される気象条件および維持管理条件下」とは何ですか? |
 |
 |
異常気象がおきず、平年時の気象が継続しており、また、入居者の方が日常の清掃や点検、簡単な補修を行っている状態でということです。維持管理について例を挙げれば、木造住宅の場合、木材が極端な湿気や雨水にさらされることがないように、雨樋などがつまらないように清掃をしていたり、換気口をふさがないよう気をつけるとか、傷んだ外壁材の補修を行っているなどのことが想定されます。その状態で、50年とか75年、大規模な改修工事がないように対策されているかどうかということを表すことになります。 | |
 |
 |
ところで、どのような対策をすれば、50年とか、75年とかと認められるのですか? |
 |
 |
木造の場合の対策は次の通りです。
木造軸組工法の住宅で等級3の使用基準の一部をあげると、次のようになります。
(1)土台・軸組・床組などについて使用機種と保存処理の方法の組み合わせがあります。
(2)地域により、防蟻措置が必要です。
(3)1階浴室廻りでは、定められた防水上有効な措置が必要です。
(4)基礎高さは、地盤面から40cm以上です。
(5)床下の換気・防湿措置や小屋裏換気に定めがあります。
また、木造軸組工法の住宅で等級2の使用基準では、(1)について若干保存処理の方法が簡易になるほかは、(2)〜(5)までの条件は変わりません。
住宅金融公庫の、耐久性要件をクリヤーしている(35年償還の対象)場合は、おおむね等級2になる程度と考えられます。
ツーバイフォー工法の住宅の場合も、(1)が少し違っているだけで、(2)〜(5)は変わりありません。住宅金融公庫の仕様で行った場合は、やはりおおむね等級2に相当する程度と思われます。 | |
 |
 |

|
|