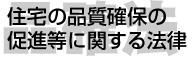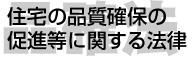|
|
| 5.温熱環境に関すること |
 |
 |
 |
 |
温熱環境に関することについて説明してください。 |
 |
 |
住宅の温熱環境の性能については、いろいろなものが考えられますが、ここでは、省エネルギー性に着目した項目として取り上げています。つまり、「省エネルギー等級」として住宅の構造躯体などへの断熱措置の程度によって、等級が決められます。 | |
 |
 |
省エネルギー等級について説明してください。 |
 |
 |
住宅の断熱化等による暖冷房に使用するエネルギーの削減の大きさについて、
| 等級4 |
エネルギーの大きな削減のための方策(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定による建築主の判断の基準に相当する程度)が講じられている。 |
| 等級3 |
エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じられている。 |
| 等級2 |
エネルギーの小さな削減のための対策が講じられている。 |
| 等級1 |
その他。 | 地域区分 I・II・III・IV・V・VI | |
 |
 |
省エネルギー等級は、具体的にどのような対策を必要とするのでしょうか? |
 |
 |
国土交通省が、これまでに制定してきた省エネルギー基準は、制定時期が後年になるほど、厳しくなってきています。つまり、エネルギー削減の大きさがだんだん大きくなっているわけです。これは地球環境問題を考えるとき、やむを得ない方向だということが言えます。
ここの等級は、どの時期に制定された基準に基づくかということで大筋が決まります。
| 等級4 |
平成11年制定の一般的に「次世代省エネルギー基準」といわれる基準とほぼ同様のもの。なお、住宅金融公庫では、250万円の割増融資の基準として、ほぼ同レベルの基準を採用しています。 |
| 等級3 |
平成4年制定の一般的に「新省エネルギー基準」といわれる基準とほぼ同様のもの。なお、住宅金融公庫では、50万円あるいは100万円の割増融資の基準として、ほぼ同レベルの基準を採用しています。 |
| 等級2 |
昭和55年制定の基準(省エネルギー基準)にほぼ適合する程度。 | | |
 |
 |
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」とは何ですか? |
 |
 |
昭和54年に制定された法律で、「省エネ法」といわれています。工場や自動車など広い範囲の省エネルギー対策が決められていますが、住宅などでも、すべての建築主は構造の断熱化などの措置に努力しなければならないとされています。このとき、建築主の判断のため国土交通大臣の告示で定める基準が、住宅の「省エネルギー基準」です。なお、この「省エネルギー基準」は、性能型の基準である「建築主の判断基準」(年間暖冷房負荷・熱損失係数など)と仕様型といえる「設計および施行の指針」があります。等級説明の中にある「建築主の判断の基準」はこのことを指しています。 | |
 |
 |
地域区分とは何ですか? |
 |
 |
省エネルギー基準では、全国を6つの地域に分け、それぞれの地域における、必要とされる性能値や仕様を定めています。平成4年の「新省エネルギー基準」では、県別に6つの区域に、平成11年の「次世代省エネルギー基準」では、さらに細かい地域別の区分で6つの区域になっています。今回の評価基準はすべて平成11年の基準の区分によることとされていますので、誤解のないようにしましょう。住宅を建設する地域が、6つの地域区分のどこに入っているかを確認して、それぞれに定められた性能値を満たす仕様や、すでに定められている仕様に適合させることが必要です。
| |
 |
 |

|
|