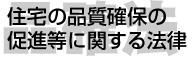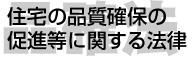|
|
| 2.火災時の安全に関すること |
 |
 |
 |
 |
「火災時の安全に関すること」には、どんな項目がありますか? |
 |
 |
戸建住宅の場合は次の4つです。なお、耐火等級については、建築基準法でいう「延焼のおそれある部分」(隣地境界線または道路中心線から、1階で3m、2階では5mの住宅の部分)があるときだけ表示します。
- 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
- 耐火等級(延焼のおそれある部分[開口部])
- 耐火等級(延焼のおそれある部分[開口部以外])
3階以上の戸建て住宅の場合
- 脱出対策(火災時)
なお、共同住宅の場合は、これら以外に感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)・避難安全対策等級・耐火等級(界壁・界床)があります。 | |
 |
 |
感知警報装置設置等級について説明してください。 |
 |
 |
自ら居住する住戸内で火災が発生したとき、早期に火災を覚知し、避難を容易にするための対策がどの程度講じられているかを表す等級です。感知器等の適切な設置によって、早く火災を察知して迅速に避難を開始できると考えています。
| 等級4 |
評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている。 |
| 等級3 |
評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。 |
| 等級2 |
評価対象住戸において発生した火災のうち、台所及び1以上の居室で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。 |
| 等級1 |
その他 |
以上のことを一覧にすると、次のようになります。
| |
感知場所 |
感知方法 |
警報対象 |
| 等級4 |
すべての台所と居室 |
早期に感知 |
住戸全域に警報 |
| 等級3 |
すべての台所と居室 |
早期に感知 |
当該室付近に警報 |
| 等級2 |
台所と1以上の居室 |
感知 |
当該室付近に警報 | | |
 |
 |
感知器や警報機の性能や設置方法はどうなっていますか? |
 |
 |
評価方法基準に定められています。 | |
 |
 |
耐火等級(延焼のおそれのある部分[開口部])について説明してください。 |
 |
 |
建築基準法では、隣の敷地からの距離等に応じて、建物の外壁等のうちで延焼のおそれのある部分を定めていることはご存じの通りです。建築する敷地や建物配置によって、延焼のおそれのある部分[開口部]がある場合は、この項目の記入が必要です。
等級3 火炎を遮る時間が60分相当以上
等級2 火炎を遮る時間が20分相当以上
等級1 その他 | |
 |
 |
耐火等級(延焼のおそれのある部分[開口部以外])について説明してください。 |
 |
 |
延焼のおそれのある部分[開口部以外]がある場合は、この項目の記入が必要で、等級は1〜4までです。
等級4 火炎を遮る時間が60分相当以上
等級3 火炎を遮る時間が45分相当以上
等級2 火炎を遮る時間が20分相当以上
等級1 その他 | |
 |
 |
火炎を遮る時間とはどんなものですか? |
 |
 |
ふつうには、耐火時間といわれるものですが、壁や窓などに使用される部材や建材が、一定の条件の下でどの程度の時間まで火に耐えられるかを試験場で測定したものです。
等級4は一般的には、コンクリート造の中高層共同住宅の基準になるのではないでしょうか。 | |
 |
 |
3階以上の戸建における脱出対策の表示について説明してください。 |
 |
 |
3階以上の部分について、日常の生活動線が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策を表示します。
□
直通階段に直達するバルコニー
□ 隣戸に通じるバルコニー
□ 避難器具 [ ]
□ その他 [
]
□
なし | |
 |
 |
避難器具とはどんなものを指しますか? |
 |
 |
避難ばしごなどと考えられます。 | |
 |
 |

|
|