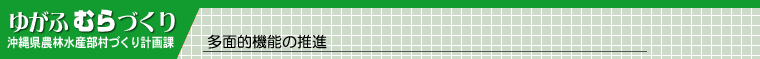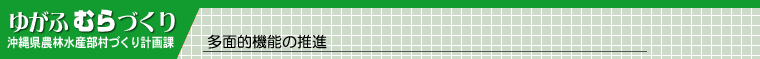| 6.意見交換 |
|
 ○崎山会長 いかがですか。今のお話、まず前半のほうは沖縄振興特別措置法の中で、いわゆる農林水産業の振興計画、そして観光推進計画として位置づけられた中での沖縄県まちと村交流促進の構想がまず紹介されました、6ページですね。 ○崎山会長 いかがですか。今のお話、まず前半のほうは沖縄振興特別措置法の中で、いわゆる農林水産業の振興計画、そして観光推進計画として位置づけられた中での沖縄県まちと村交流促進の構想がまず紹介されました、6ページですね。
続いて7ページの、具体的な沖縄県まちと村交流促進構想の概要ということで紹介をしてもらいましたけれども、一気に紹介をしましたので、いろいろと質問等もあるかと思います。委員の中からどうですか。皆さん、感じたことを含めて、あるいは疑問点も含めて何かありましたら。大変いろいろと盛り込まれているものですから、ちょっと整理しながらですけれども、委員の方々のそれぞれの現場からの提言あるいは疑問なども含めて、話を進めていくことができたらなと思うんですが。
はい、石原さんお願いします。 |
○石原委員 6ページと7ページを、ちょっと関連しての意見です。
この6ページには、上位計画が書いてありまして、この上位計画が沖縄振興計画が上位計画であるというふうにとらえてよろしいですか。それで、次のページのところなんですけど、右側の基本方針の上のほうに、この上位計画の目的、もう1回6ページに戻りますけど、この沖縄振興計画の中で、この交流促進計画の関連するところは、(4)のウ「多面的機能を生かした農山漁村の振興」ですよね。これが上位としてあって、この計画をすることによって、多面的機能を生かした農漁村の振興を図るためにこの計画をつくりますよということですから、目的のところにやはり「多面的機能を生かした農漁村の振興を図り」その上の、もう1つ上の概念、「環境共生型社会をつくる」とかみたいな、大きな目的をそこにも入れて関係性が見えるようにしたほうがいいんじゃないかと思うんです。
そうしたら、自分たちのこの部分別の計画が、結果的にどういうところに貢献していくか、つながっていくかというのが、みんなが共有しやすいと思うんですよ。やはり、2つのものを見て、なかなかピンとこないですから、そこを方針の上に目的をぜひ入れていただきたいなと思うんです。これは、意見、提案です。その上位計画の目的をぜひ入れていただきたいなと思うんです。 |
| ○崎山会長 いかがですか。私も個人的に賛成なんですけども、事務局としていかがでしょうか。今の指摘ですね。 |
| ○根間班長 これに関しては、今からまたどんどん意見を聴取して、まとめて固めていきますので、そういうことも視野に入れながらまとめさせていただきたいなと思います。 |
| ○崎山会長 あったほうが、非常に共有できるというか理解しやすいですね、私たちも。そう思いますけども。 |
 ○石原委員 それともう1点なんですけど、7ページのほうの課題のほうなんですね。私がこの中で一番課題としてとらえてほしいところが抜けているなと思うんですね。それは、他の施策の連携・補完というのをぜひ入れてほしいんです。例えば、このツーリズムで、今、地域離島課というところが体験滞在型交流事業というのをやって、もう7〜8年になると思うんです。これは沖縄振興計画の中で、全国の中でも沖縄県だけが特別な補助金があって、こういう7〜8年ももうやっているんです。それで、この体験滞在型交流事業というのは、相当県内各地に指定されてやっているんです。やっているところが実際どういうことやっているかというと、7ページの右側の役割分担ってあります、あれに似たようなことをモデル的にやっているんです。2カ年くらい、大変な補助金をもらってやっているんです。建物もつくっているんです。 ○石原委員 それともう1点なんですけど、7ページのほうの課題のほうなんですね。私がこの中で一番課題としてとらえてほしいところが抜けているなと思うんですね。それは、他の施策の連携・補完というのをぜひ入れてほしいんです。例えば、このツーリズムで、今、地域離島課というところが体験滞在型交流事業というのをやって、もう7〜8年になると思うんです。これは沖縄振興計画の中で、全国の中でも沖縄県だけが特別な補助金があって、こういう7〜8年ももうやっているんです。それで、この体験滞在型交流事業というのは、相当県内各地に指定されてやっているんです。やっているところが実際どういうことやっているかというと、7ページの右側の役割分担ってあります、あれに似たようなことをモデル的にやっているんです。2カ年くらい、大変な補助金をもらってやっているんです。建物もつくっているんです。
そしたら、これとこのこれとの関係が、課が違うもので、あれは企画部にあるんです。これは農林水産部にあるものですから、やっぱりそういうふうなところを、今後基本的に基本計画とかつくる中で、例えばそういうところも私、具体的に意見を言っていきたいなと思っているんです。 |
| ○根間班長 これに関しては、去年、観光の部分で、県の内部で連絡会議をもっていますので、この構造に関しても、県の組織の内部の意見もみんな聞くという、次の考え方をもっていますので、その中でそういう連携のあり方を、どういうふうに、観光との部分というのを… |
○石原委員 農林水産でこれだけ班のプロジェクトができたというのは、ものすごい私も評価していますし、きょうこれだけ皆さんスタッフの職員の方がいらしてすごいなと思って、何か私もすごくうれしいなと思って、できるだけ自分も一生懸命かわりたいなと思ってはいるんですけど、問題は、現場の人が地域にいる人たちがそういうこと知らないし、情報が来ないんです。だから実際に体験滞在って、私、地域離島振興局のほうに8年くらい嘱託で関わらせていただいたんで、それで申し上げるんですけど、結局地域のツーリズムやっている人たちというのは、もう次から次から来るものに、結局やる人は一緒なんです、地域でやる人は。どこからこれが来るかというのが、もう全く雨あられのように飛んできて、あとはわからんというのが現実なんです。
だから、地域の人たちにそういう情報を与えて、ちゃんと行政としてはこうやっていますよ、地域の人がやるときには、 こういうふうなことを組み合わせたらどうなったらいいと思いますかという、その間のコーディネートがないんです。そのために地域の人たちは、補助金があっちこっちからきて混乱しているというのはみんな課題だというんですけど、そこをやっぱり今回、せっかくのツーリズムでここまできていますから、踏み込んでいただきたいなというのがありまして、やっぱり課題の中に、できれば入れていただきたいな。これは現場の人の、これも私ぜひ聞きたいんですけど、私はコーディネートする側で地域に入っていくものですから、結構そういう声を私は耳にするんです。だからそこも、どうですか、今回この会からまたそういうのも提案出たら、私はいいなと思っているんですけど。 こういうふうなことを組み合わせたらどうなったらいいと思いますかという、その間のコーディネートがないんです。そのために地域の人たちは、補助金があっちこっちからきて混乱しているというのはみんな課題だというんですけど、そこをやっぱり今回、せっかくのツーリズムでここまできていますから、踏み込んでいただきたいなというのがありまして、やっぱり課題の中に、できれば入れていただきたいな。これは現場の人の、これも私ぜひ聞きたいんですけど、私はコーディネートする側で地域に入っていくものですから、結構そういう声を私は耳にするんです。だからそこも、どうですか、今回この会からまたそういうのも提案出たら、私はいいなと思っているんですけど。 |
| ○崎山会長 どうでしょうか、よく縦割りの話がいつも出てきて、克服できたようで、県の中の行政の分化というのは、まだまだ私は後れているのではないかなと、私なりに思っているのですが。そういう意味での、今、他の施策との連携というのは、位置づけですよね。部署が違うと全く違った表情になって、要するに出口でつながらないところがあるんです、今、石原さんおっしゃったように。 |
| ○根間班長 先ほど申し上げたように、県の内部のほうでも、2カ月に1回こういう連絡会議を去年からもっていますので、そのあたりどんどん、どういうふうな連携プレーすればいいかということを、意見提言していきたいなと。それだけのことも、先ほど申し上げたように、そういう面での連絡会議ができていますので、局のほうともしっかり連絡とって、どういうふうに仕組んでいけばいいかということに関して、やはり今さっき申し上げたように、地域のニーズにどう関わっていくかということが、やはり視点になると思いますので、そういうふうにしていきたいと考えております。 |
| ○崎山会長 どうですか、今、6ページと7ページに集約されたお話になっていますけれども、お読みになって、説明をお聞きになって、疑問点、あるいは意見、それからぜひこれはこの視点が抜けているというふうな形の現場からの声があるといいなと思いますけれども。 |
 ○花谷委員 インストラクターとの人材育成というところなんですけれども、私たち受け入れしてからお客さんをご案内したりとか、いろいろなことを体験などをやっていくわけですけれども、本業をしながらなので、それをおろそかにもできない、そういう中でお客さんの受け入れをしていくわけなんです。県の方からとか、石垣市の方からとか、人材育成のための講座に出席できるような助成金をもらうことがあるんです。東京行って3泊4日とか4泊5日ぐらいで研修受けて帰ってきて、インストラクターの資格とかエスコーターとか、ファームインの養成講座の資格とかいただいてくるんですけれども、そうすることもやっぱり本業をおいて、放ったらかして行かなくてはいけないという大きな負担があるわけです。それをまだ、でも十分に生かしきれてないという、そういう部分もありまして、できたらそういうコーディネーターがたくさん地域にいてほしいんです。特別な人が、一部のお金をいただいて行かせるっていうだけじゃなくて、みんなでそういうことができるようになりたいというのがあるんですけれども、そのためにはわざわざ東京まで出かけていかないで、県の段階で、そういう講座ができたら、いろんな人が参加できるようになるんじゃないかなって、こういう人材育成につながるんじゃないかなって思います。 ○花谷委員 インストラクターとの人材育成というところなんですけれども、私たち受け入れしてからお客さんをご案内したりとか、いろいろなことを体験などをやっていくわけですけれども、本業をしながらなので、それをおろそかにもできない、そういう中でお客さんの受け入れをしていくわけなんです。県の方からとか、石垣市の方からとか、人材育成のための講座に出席できるような助成金をもらうことがあるんです。東京行って3泊4日とか4泊5日ぐらいで研修受けて帰ってきて、インストラクターの資格とかエスコーターとか、ファームインの養成講座の資格とかいただいてくるんですけれども、そうすることもやっぱり本業をおいて、放ったらかして行かなくてはいけないという大きな負担があるわけです。それをまだ、でも十分に生かしきれてないという、そういう部分もありまして、できたらそういうコーディネーターがたくさん地域にいてほしいんです。特別な人が、一部のお金をいただいて行かせるっていうだけじゃなくて、みんなでそういうことができるようになりたいというのがあるんですけれども、そのためにはわざわざ東京まで出かけていかないで、県の段階で、そういう講座ができたら、いろんな人が参加できるようになるんじゃないかなって、こういう人材育成につながるんじゃないかなって思います。 |
○崎山会長 切実だと思います。八重山、宮古もそうですけれども、特にまた沖縄でも、むしろ山原から来る場合は、喜友名さんなんかは飛行機よりかえって時間かかったりするわけですね。そういう意味で、さらに負担を受けて、東京へ行ったりするというのは、本当にちょっと大変だと思うんですけれども。
いかがですか、今のこのインストラクターあるいはコーディネーターの。 |
 ○津嘉山委員 これは私たちもインストラクターの研修に行ったときに、これが宮古でできないものかなと思ったんです。あの先生たちを呼んでやるのと、私たちが行くのと、どこがお金かかるのかなと、みんなで話していたんです。私たちはむしろ県のことがわからなくて、助成金が降ってくるとかというと、どこに助成金が降ってきているのかなとか、わからないんです。どういう活動でどういう内容で、助成金が使われているのかもわからないんです。その助成金を使ってできた事業が、どういうふうにやっていっているのかも、本当に内容をわからないんです。 ○津嘉山委員 これは私たちもインストラクターの研修に行ったときに、これが宮古でできないものかなと思ったんです。あの先生たちを呼んでやるのと、私たちが行くのと、どこがお金かかるのかなと、みんなで話していたんです。私たちはむしろ県のことがわからなくて、助成金が降ってくるとかというと、どこに助成金が降ってきているのかなとか、わからないんです。どういう活動でどういう内容で、助成金が使われているのかもわからないんです。その助成金を使ってできた事業が、どういうふうにやっていっているのかも、本当に内容をわからないんです。
そこら辺ももっともっと知りたいなと思いますし、そして、インストラクターの平成14年からかけてやっている、終わっている皆さんが、どういうふうにそれを生かしているか、インストラクターとしてどういうふうに活用しているかというのも全然見えないんです。ただ研修受ける、研修受けるって。積み重ねでパンクしそうですから、もう体でも頭でもいっぱい勉強しましたので、それを本当に実際に活用する場というところが必要じゃないかなと思いますね。 |
| ○崎山会長 ほかの地域どうですか、喜友名さんなんかも。 |
 ○喜友名委員 私もインストラクター受けたんですけど、ある山に行って、山の散策をしながら、いろんな話をしながら、何かをつくり上げていくという、要するに案内人のちょっと体験型案内人というか、県外で、東京で。 ○喜友名委員 私もインストラクター受けたんですけど、ある山に行って、山の散策をしながら、いろんな話をしながら、何かをつくり上げていくという、要するに案内人のちょっと体験型案内人というか、県外で、東京で。
東村あたりは、その方たちを呼んで、東村の20名か何名かにこの講座をやったそうです。その資金が、東村がお金出して、確か100万、200万円単位のお金だったと思います。東村にはだからインストラクターがいっぱいいるわけです。ただ今言ったように、それをうまくコーディネートする、エスコーターがあって、インストラクターがあって、あとコーディネーターといいました。このインストラクターは、現場ですよね。あと、インストラクターを動かすコーディネーターの分野を受けないと、計画ができないわけです。それを各農家でやるときには結構大変なもの。普及者がうちの北部のほうは行っています。
だから、今言ったコーディネーターをやっぱり必要、動かすために。それは課題だと思います。今現在、私たち山原グリーン・ツーリズムは、生みの親は北部農業改良普及センターです。普及センターが勉強をさせて、私たちが生まれました。ただ、今現状は、南、中、北部ありますけれど、普及センターによって係を張り付けできないところも出ているそうです。市町村、県のほうは、今頑張ってグリーン・ツーリズムやりなさいと言っているんだけど、実際、現状で、現場で、役場とか市町村によって、全然それがわからない、はり付け歩いていない。だから、窓口がわからないという、すごい矛盾している、県の方針と現場と。全然矛盾感じて、私たちのグリーン・ツーリズムも一体、本当は商法のほうのグリーン・ツーリズムに入るんだけど、農村グリーン・ツーリズムじゃなくて。結局はその人たちも拾い上げて勉強をしているわけです。一緒に上がっていくために。だから、温度差とか、地域差があります。だから、それをどうやって今県のほうは市町村に伝えているのか。どんな伝え方をしているのか。私たちの声に届いてないわけです。
それを、ちょうど力をつけてきたときなんです。今引っ張ってくれたら、きっと私たち、下のほうたちは、もっともっと頑張っていけるなって思いがあって、今がチャンスなんです。だから、よろしくお願いしたいんです。 |
○崎山会長 先ほどの石原委員の話に全部見事につながっているような気がするんですけど。
どうですか、今……。 |
○根間班長 ちょっと5ページご覧になっていただきたいなと考えております。
今まで19年3月、きょうの第1回会議を主催しているわけですけど、今後、構想をちゃんとしたものにしておくためには、どうしてもメーリングリストを作成して、お互いの意見を聞いて、それと委員の皆様方の意見をまたまとめて、関係各課にみんな投げます。そういう中で、現場にも入っていって、実際の現場の人たちの意見を、何が課題で、あるいは課題じゃないかもしれないわけです。何が本当に困って、何が課題なのかなと。そういうところから、ぜひこの構想を立ち上げていきたいなというふうに考えておりまして、きょうはまだ第1回ですので、いろんな意見を賜って、その中で私どものまた班の中で、内部でまた揉んで、ほかのところからも意見を徴集して、先ほどの関係機関との連携というのもございましたので、そのへんもみんな意見聴取して、本当に地域に役立つような構想にしていきたいなというふうに段取りしております。 |
|