自立支援医療(精神通院)
「自立支援医療」とは、障害者等につきその心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活を営むために必要な医療です。これまでの精神通院医療精神保健福祉法第32条)の根拠法が平成18年4月より障害者自立支援法に移行し、平成25年4月からは障害者総合支援法になりました。自己負担額が5%から原則10%となり、所得等により自己負担上限額が設定されます。また、指定医療機関制度が導入され、病院・診療所のみならず、薬局、訪問看護事業所も指定されます。また、届け出た医療機関以外では公費は適用されません。
制度の概要
対象者
精神保健福祉法第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるものです。なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために、なお通院医療を継続する必要のある場合も対象となります。
有効期間
- 新規申請の場合には、市町村が申請を受理した日を始期とし、その始期から1年以内の日で月の末日たる日を終期とします。
- 再認定の申請の場合、前回支給認定の有効期間の満了日の翌日を始期とし始期より1年以内の日で月の末日たる日を終期とします。(前回支給認定の有効期限を徒過した場合の申請は新規申請と同様の取り扱いをする。)
- 変更申請(所得区分)の場合は、保健所で変更することを決定した日の属する月の翌月の初日から新たな所得区分に変更するものとします。
- 指定医療機関の変更申請の場合は、保健所で変更することを決定した日以降から新たな医療機関に変更するものとします。(これまでのように市町村の受理日からではないことに注意)
対象医療機関
指定医療機関制度が導入され、病院・診療所のみならず、薬局、訪問看護事業所も指定されます。届け出た医療機関(受給者証に記載)以外では公費は適用されません。
申請者
障害者本人または保護者が申請できます。
申請方法
居住地(実際に住んでいる場所)の市町村の精神保健福祉担当窓口に必要書類を提出し、沖縄県知事に申請します。
自己負担限度額(自己負担限度額認定フロー図↓参照)
定率10%負担となり、所得等により一月当たり自己負担上限額が設定されます。
- 生活保護世帯:0円
- 市町村民税非課税世帯(受給者収入80万円以下):2,500円
- 市町村民税非課税世帯(受給者収入80万円超): 5,000円
※上記以外の方で「重度かつ継続」に該当する場合も上限額が設定されます。
- 市町村民税額(所得割)3万3千円未満: 5,000円
- 市町村民税額(所得割)3万3千円以上23万5千円未満:10,000円
- 市町村民税額(所得割)23万5千円以上: 20,000円
※ただし、法の施行後3年間の経過措置市町村民税額(所得割)23万5千円以上の世帯で「重度かつ継続」に該当しない場合は、制度の対象外となります。
沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度
沖縄県の場合「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用されますので、認定された自己負担額は従来どおり公費負担となり、自己負担は生じません。ただし、訪問看護事業所の訪問看護については、特別公費負担制度の対象にはなりません。
沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度とは
「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」の施行に伴い、沖縄県においては、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令108号)」第3号の規定により、通院に要する医療費の本人負担分についても全額を公費負担する特別措置が講じられています。
自立支援医療費自己負担限度額認定フロー
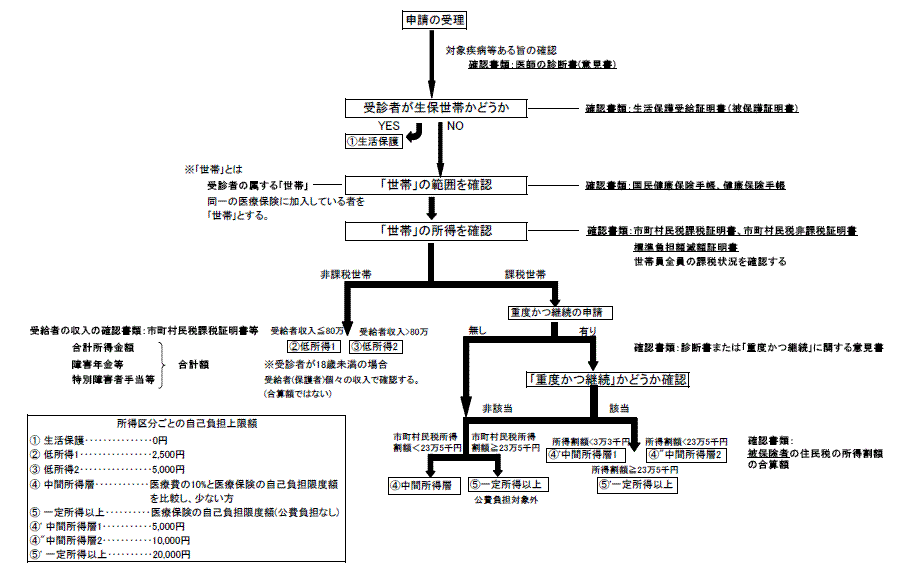
申請手続き
必要な書類は「申請の種類等」によって異なります。
※様式は沖縄県の様式を使用して下さい。
(1)新規・再認定の申請をする場合
- 申請書「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」様式第1号
- 診断書「精神障害者保健福祉手帳・通院医療費公費負担用」様式第2号
※(重要)平成22年4月認定分の申請から診断書の提出方法が変わりました。 - 医療保険者証の写し(生活保護受給世帯で医療券を利用している方は不要)
個人ごとのカード型保険者証の場合は:被保険者と受給者の分のカードのコピー - 所得区分によって
- 生活保護受給証明書
- 市町村民税の課税・非課税証明書(「世帯調書及び税額証明書」(別紙2)でも可)
- 受給者の収入が確認できる書類
- 高額治療継続者の該当者であることを証するもの
(診断書に記入欄が無い場合は「重度かつ継続」に関する意見書(様式第3号))
- 同意書(別紙3)
※職権により申請者の課税状況等を確認する場合に必要 - 再認定の場合は「受給者証」(写し)
- 個人番号確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カード、個人番号記載の住民票等)
- 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書の場合は1点、顔写真が付いていない証明書等の場合は2点必要)
(2)精神障害者保健福祉手帳の申請と同時に、新規・再認定の申請をする場合
- 申請書(「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」)様式第1号
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 診断書(「精神障害者保健福祉手帳・通院医療費公費負担用」様式第2号
- 前記(1)の3以降
(3)他都道府県からの転入の場合
自立支援医療では他都道府県から転入した場合は、再度県内において「新規申請」をしてもらう。手順は前記(1)と同様。
※但し、他都道府県で認定された診断書(写)で申請する場合は、受給者証の有効期限は他都道府県で認定された期限までとなります。また、次回更新時には沖縄県様式による診断書の提出が必要となります。
(4)「受給者証」の支給認定の変更申請の場合
- 申請書(「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」)様式第1号
- 既に交付されている「受給者証」(原本)
- 保険の種類の変更により自己負担上限額に変更が生じる場合
※必要に応じて
- 生活保護受給証明書
- 市町村民税の課税・非課税証明書(「世帯調書及び税額証明書」(別紙2)でも可)
- 受給者の収入が確認できる書類
- 高額治療継続者の該当者であることを証するもの(「重度かつ継続」に関する意見書 (様式第3号))
(5)「受給者証」の記載内容の変更手続きの場合
- 届出書(「自立支援医療受給者証等記載事項変更届」(様式第5号))
- 既に交付されている「受給者証」(原本)
窓口で原本を訂正し、そのコピーを保健所へは進達(原本は窓口で申請者へ即返却)
(6)「受給者証」を紛失した場合
申請書(「再交付申請書」様式第6号)
(7)その他
- 申請は必要書類をすべて揃え、郵送で行うことも出来ます。(郵送申請において、土日祝日・休日・年末年始に届いた場合は翌市町村開庁日が精神保健福祉担当窓口の受付日となります。)
- 指定自立支援医療機関(医療機関、薬局、訪問看護等)の変更申請については県の承認日からの利用になりますので、3~4週間余裕を持って申請をして下さい。
※変更申請承認前に変更先の医療機関等を利用した場合は自己負担になります。 - 新たに医療機関等が指定を受ける場合、医療機関が県に申請書を提出し、指定の決定を受けた日の属する月の翌月を初日として指定年月日とするため、 指定を受けていない医療機関への変更申請は出来ません。
※医療機関等が指定されていないと、変更申請も承認できず、医療機関が指定を受け変更申請が承認されるまでの間に変更先の医療機関等を利用した場合、自己負担になります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 総合精神保健福祉センター
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212-3
電話:098-888-1443 ファクス:098-888-1710
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
